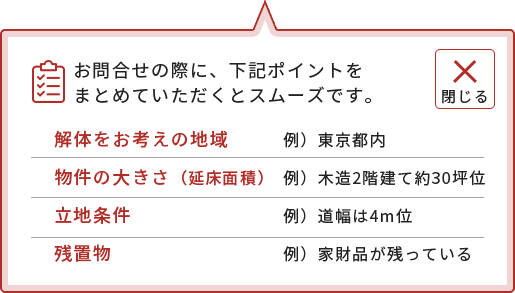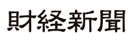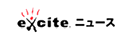《解体小説》内装解体編・第二章
第二章 「戦意喪失」

前テナントの人気美容室というのは読んで字の如く、四年前の開店以来売り上げは右肩上がりで、最低一ヶ月前には連絡を入れなければ希望の時間帯で予約が取れないほどの人気店だ。在籍する美容師の技術や人当たりはもちろん、空間自体の居心地の良さにも定評があったらしい。確かに俺が交渉のために足を運んだ時も、客として通うならこんな店が理想的だ、と直感したものだった。当然ながらファンも多く、特に近所に住むリピーターなどは移転を心底残念に思っただろう。
そんな店の後釜に座り続けることが、どれほどハードルの高い行為だったのか。
深く考えもせず飛び込んだことを、正直、今になって後悔している。
開店から数十日。
人気店の熱も冷めやらぬうちに同じ場所で同じ業種の開店とあれば、客の期待や好奇心もにわかに高まったことだろうと思う。
そんな期待に応えようと、カットやパーマ、シャンプーの腕・サービスの質……美容師としての土台になる部分については毎日ストイックに磨き続けた。そうしているうちに自分の中のこだわりが顔を覗かせ、気に入っていた内装も自分仕様に造り替えたいと思い始めるのは当然の流れだった。
しかし、人気店の知名度ありきで集まった客が求めていたのは、あくまでその「代わり」となる店に過ぎなかったのだ。わざわざ他県まで足を運ばなくても、馴染みの場所で美容師の腕もまずまずのクオリティが期待でき、居心地の良さは以前のまま――これらを無くして、今の店に付いている客のロイヤルティはほとんどゼロと言ってしまって差し支えのないものだった。裏を返せば、このいずれかの要素を失った瞬間に、彼らは県を跨いででも通い慣れた店に舞い戻ってしまうだろう。さもなければ、新たな美容室を探し始めてしまうかもしれない。
正直なところ、俺の美容師としてのスキルは “上の中”くらいにに置しているという自信はあった。ただ、勤めていた美容室の同期達と比べて頭一つ抜けているかと言われれば、首を横に振らざるを得ない。
だからこそ前テナントの存在が常に脳裏にちらつき、早く追い付かなければ、いやもっと個性を出していかなければと、焦る気持ちが止め処なく押し寄せていたのだ。
そして数ヶ月間のリニューアル期間を終える頃には、迷走っぷりを感じ取ったらしい客達が少しずつ離れていくのを感じていた。自分の個性を出したいがために、彼らが落ち着ける空間さえも脅かしていたのだ。
接客サービスすら「戸坂さん、最近お客さんに干渉しすぎですよ」とアシスタントの槙田に幾度も指摘されていたが、あまり耳を傾けていなかった。頭では理解していたのかもしれないが、少しでも客との距離を縮めたいと思うあまりに行動が伴わなかったのだ。
独立してやっていくにはまだ早すぎたんじゃないのか。
そもそも、経営者になれる器なんか持ち合わせていなかったんじゃないか――
ついに耐え切れなくなった俺は、黙々と掃除をしている槙田の背中へ半ば無意識に話しかけていた。
「……やっぱり俺、美容師には向いてなかったんだろうか」
「どういうことですか?」
「ここ最近ずっと空回りしっぱなしだし、お客さんの要望と自分の理想が食い違ってることすら気付けないでいた。目の前の感情に気を取られて、店の空気作りが疎かになっている。しかも――」
「それは美容師に向いてないんじゃなくて、経営者に向いてなかっただけなんじゃないですかね。戸坂さん、腕はそれなりにあると思うんで」接客はちょっとしつこいですけど、と小声で付け足したのを聞き逃さなかったが、触れずに話を続けた。
「俺一人の力だったら、一年近くも保ってなかったと思うんだよ。槙田のキャラが受けているのもそうだし、何より元々入っていた美容室の知名度によるところが大きい。けど、未だにその看板に縋りつかなきゃやっていけないのは悔しいだろ。そこで悩むくらいだったら、……お前には悪いけど、いっそ潔く閉店して、一からやり直そうかと思ってる」
いつもなら間髪入れずに返答する槙田だが、この時ばかりは少しの間を置いてから、こちらを見ずに口を開いた。
「……店畳んで従業員の一人に戻るのも、また別の場所で店開くのも戸坂さんの自由ですけど、――俺はその行く末を見届けられないんで、すいません」
「……え?」
「実は俺、ちょうど今年いっぱいで辞めさせてもらおうと思ってたんですよ。すでに知り合いのサロンから声も掛かってて……。こんなタイミングで本当申し訳ないですけど」
槙田が辞める? まさか。
そんな気配は微塵も感じられなかっただけに、俺はひどくショックを受けた。
槙田は開店して間もなく募ったアルバイトに応募してきて以来、何だかんだ二年近く店を支えてくれていたのだ。きっとこのことを打ち明けても、彼なら付いて来てくれるだろう――そんな淡い期待も抱いていたのに。
「……そうか。まあ、そりゃお前くらいの個性があれば声も掛かるわな。でも流石に、ウチの最後くらいは見届けてくれるよな?」
精一杯の強がりを込めてそう言い放ち、返事を待たずに片付けの作業へと戻った。